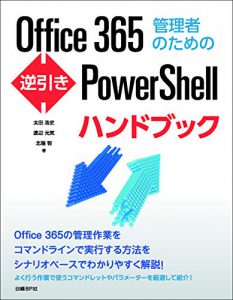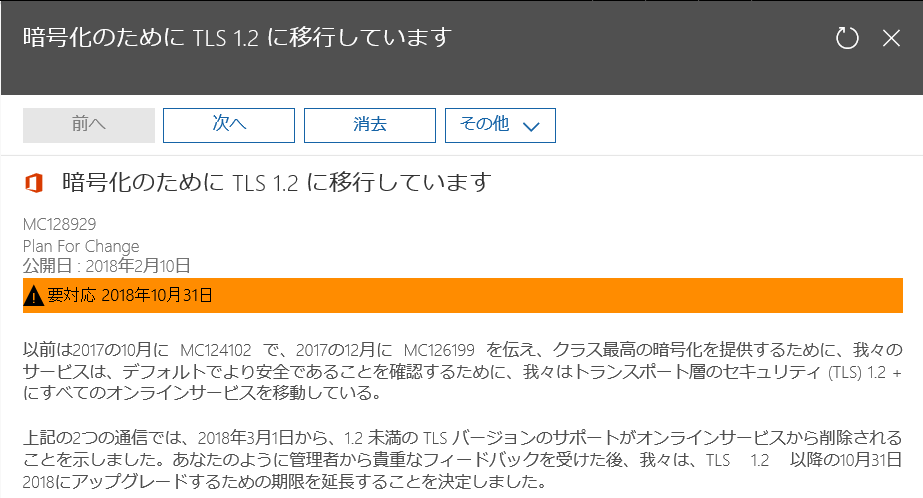YubiKeyでの運用で気を付けなければならないのは、キー自体を忘れたときの管理です。代替の方式として個人のスマートフォンでの電話やMicrosoft Authenticatorや固定電話などが設定できる環境であればそれで代替してもいいですが、今回はセキュリティの強度が高いとして推奨されている予備のYubiKeyを用意する方法について、どう利用するかの例を紹介します。
もちろん、各個人に2個ずつ YubiKey を配布し、一つは会社の机の中に入れておくなども可能かと思いますが、5000円程度するデバイスなので数がまとまると結構な「合鍵」代となってしまい、二の足を踏んでいるところをよく見かけます。
ただ、ここで合鍵代をケチったばかりに職場へのスマートフォン端末持ち込みを許可させたりというのも本末転倒ですよね。